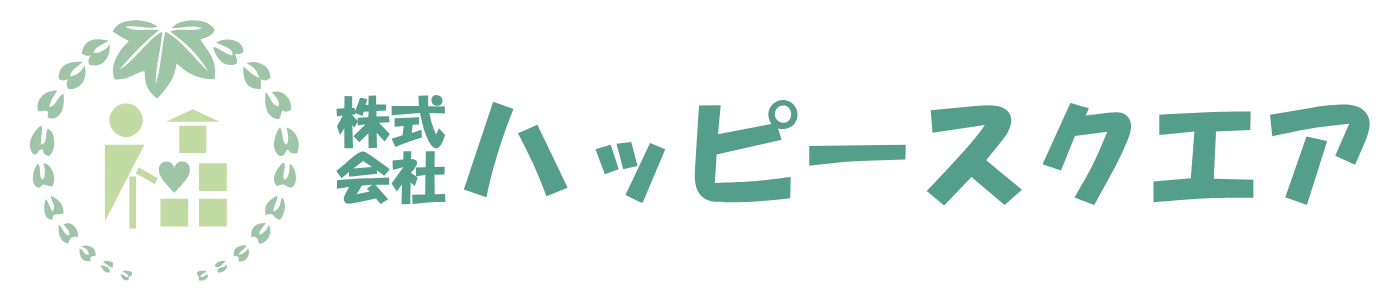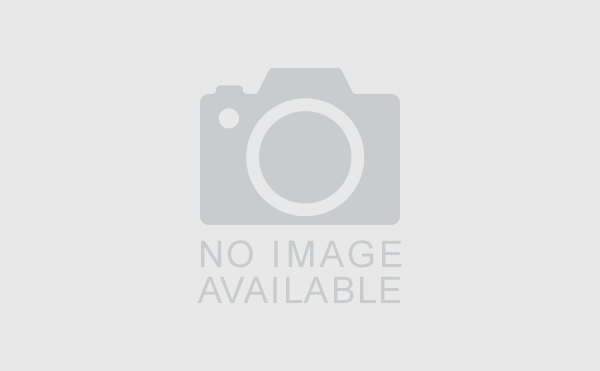🌞【ご報告】2025年上半期を終えてのご挨拶と、福祉業界の「今」
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、当社のブログを更新させていただきます。
代表の福原です。
🌻2025年上半期を無事に終えて
まずは、2025年上半期が無事に終了いたしましたことをご報告申し上げます。
これもひとえに、日頃より当社の事業にご理解とご協力をいただいておりますご利用者様、ご家族様、関係機関の皆様、そして何より現場で尽力してくれた全スタッフのおかげです。
心より感謝申し上げます。
上半期は、[ご利用者及びご家族、そして関係機関との連携強化】【現在のサービスを体系的に見直し質を高める]など、新たな挑戦・インフラ整備と既存事業の深化を進めてまいりました。
下半期も、皆様の期待に応えられるよう、スタッフ一同、より一層邁進してまいる所存です。引き続きのご支援、ご指導をよろしくお願いいたします。
💡昨今の福祉業界ニュース:2025年上半期の動向
さて、皆様もご存知の通り、福祉業界は現在、大きな変革期を迎えています。
特に2025年上半期は、今後の業界の方向性を決定づけるような重要なニュースが相次ぎました。
1. 訪問介護事業所の倒産が過去最多を更新
東京商工リサーチの調査によると、2025年上半期の訪問介護事業所の倒産件数が過去最多を更新しました。
- 主な要因: 2024年度の介護報酬改定による基本報酬の引き下げや、深刻なヘルパー不足が経営を直撃しています。
- 現状: この倒産の波は、小規模な事業所に留まらず、中堅規模の事業者にも広がっており、地域包括ケアシステムの要である在宅サービスに大きな影響を及ぼしかねない状況です。
2. 介護人材確保に向けた「光」と「影」
一方で、人材確保に向けた明るい兆しも見えています。
- 特定技能外国人の訪問介護解禁: 2025年4月より、特定技能・技能実習生による訪問介護の提供が解禁されました。外国人材の受け入れに積極的な事業所が大幅に増加しており、深刻な人手不足の新たな突破口として期待されています。
- 処遇改善効果: 複雑だった複数の加算が**「介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。これにより、事務負担の軽減とともに、賃金改善がより確実になり、介護職員の離職率が過去最低を記録**するなど、人材の定着に良い効果が現れてきています。
3. 介護支援専門員(ケアマネジャー)制度の大幅見直しへ
現場の介護支援専門員(ケアマネジャー)の負担軽減と人材確保に向けた、長年の課題であった制度の改正が、いよいよ具体的に動き出しました。
- 更新制度の廃止方針: 厚生労働省は、現行の5年ごとの資格更新制度を廃止する方針を固めました。これにより、ケアマネジャーの時間的・経済的な研修負担が大幅に軽減される見込みです。
- 受験要件の緩和: 資格試験に必要な実務経験が「5年から3年」に短縮される案も示されました。これは、新たな担い手の参入を促すための重要なステップとなります。
🤝今後の展望:私たちが目指すもの
業界全体が厳しい環境に直面している今だからこそ、当社の存在意義が問われています。
当社は、この波を乗り越えるために、以下の三点に注力し、質の高いサービスを提供し続けることをお約束いたします。
- 「ベテランスタッフを中心に据えた指導育成業務の徹底」(平均経験年数約15年)
- 「特に新人スタッフの待遇改善と専門性向上への投資」(未経験~5年目までのスタッフが居りませんので新人採用を強化します。)
- 「地域連携を強化し、真に必要とされるサービスの提供」
今後も、業界の動向を注視しつつ、地域社会に貢献できる事業運営を目指してまいります。
📝代表の言葉:原点に立ち返る勇気
最後までお読みいただき、ありがとうございます。ここからは、現場を預かる代表としての私個人の思いを綴らせていただきます。
この上半期は、正直に申し上げて厳しい局面の連続でした。特に人材不足のニュースに触れるたび、私自身も深く悩まされます。
そんな中、先日、ご利用者のご家族様から**「みなさんの笑顔が見られたから頑張れる」**という言葉をいただきました。
その一言に、私たちが原点に立ち返る勇気をもらいました。
【日々の感謝と「丁寧なお仕事」について】
これを**「日日是好日」**と認識し行動に移すことが、より良い生活と社会の発展につながるものと信じてやみません。
そして、久しぶりに穏やかな日曜日です。先日ツイッターでもご報告の通り、スタッフの体調不良などでシフト変更が鬼のようにありました。僕も久しぶりの現場に入ることが多く、急な変更で伺うことが多かったのですが、皆さん嫌な顔せず快くお迎えくださったこと、感謝の念に堪えません。
この「丁寧なお仕事」の証明として、当社は、第三者評価の受審を受けることにしました。(該当事業は障害福祉サービスの居宅介護です)
評価項目の中身を工夫し、誰もが受け入れやすい環境を整えることで、ご利用者・役所・事業所にとってより良い、公正明大な事業運営を実現できると確信しています。
【福祉の本質と、ケアマネ制度への提言】
先に触れた介護支援専門員(ケアマネジャー)の制度見直しのニュースは、長年現場に携わってきた者として、「ようやく重い腰が上がったか」という印象です。
介護保険法施行から25年が経過しました。この制度上の欠点の「あおり」を、現場のケアマネジャーが時間と金銭を対価に支払い続けている構図は、次世代の担い手が育たず、人手不足が深刻化する最大の要因の一つです。
また、主任ケアマネ制度の創設による新規参入の抑制は、市場の「ガラパゴス化」を招き、質を高めあう競争原理を阻害しています。
**「新しい制度」という言葉から脱却し、「成熟した社会インフラ」**としての介護保険法の法整備が求められます。
しかし、革新的な提案が困難を極める今だからこそ、私たちにできることは、**「目の前のお仕事を確実に、そして丁寧にしたうえで、社会に対し提案し続けること」**です。
それこそが当社の存在意義だと考えます。
【利用者様の声こそ真実】
最後に、先日、専門学校の友人からメッセージが久しぶりに届きました。彼女は教員から学年で最優等生と言われており、対して僕は「最劣等生」と言われていました。
例えば、僕が授業中に「自分は食後6時間で排泄がある」と言った際、「医学的にありえない」とありえない勢いで叱責されたことがあります。しかし、介護士として働き、勉強を重ねた結果、僕はIBS(過敏性腸症候群)であると判明しました。
当時の教員は、一部の学生の話を聞かず、医学知識を押し付けてくるのが日常でしたので、若かった僕しょっちゅう噛みついていたものです。
僕の知識が浅かったことも事実ですが、劣等生と言われたからこそ勉強を頑張ることができたのも事実です。
そして、僕が確信しているのは、**「たとえ医学とは異なっていたとしても、僕は利用者の声が真実だと認識したうえで支援やケアを工夫していくのが福祉の本質」**だということです。
知識や技術は、その声の上に成り立つものです。
そんな最劣等生だった僕ですが、その友人が今、とある施設の施設長になったそうです。そんな我々がまだ仲良くしていることを、天国にいる例の教員はどう思うのでしょうか。
僕の仕事のバイブルである映画**【最強のふたり】**を改めてお勧めし、結びとさせていただきます。
さぁ下半期も、現場の熱意を経営で支えていきますよ!!