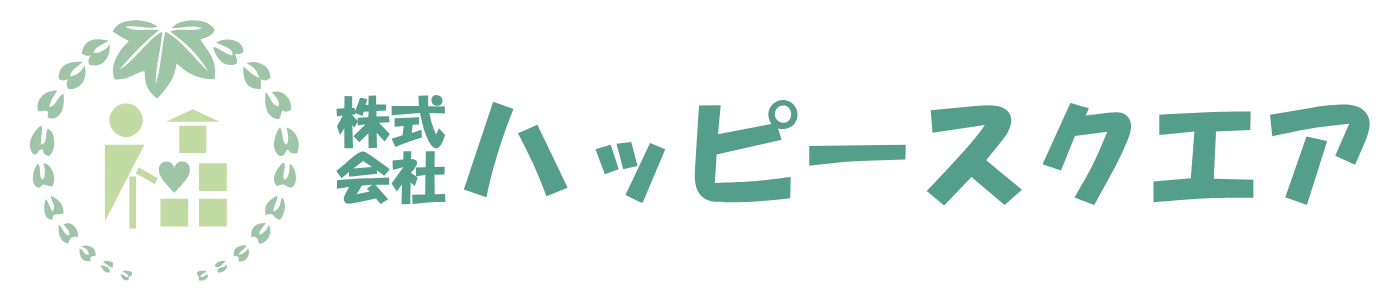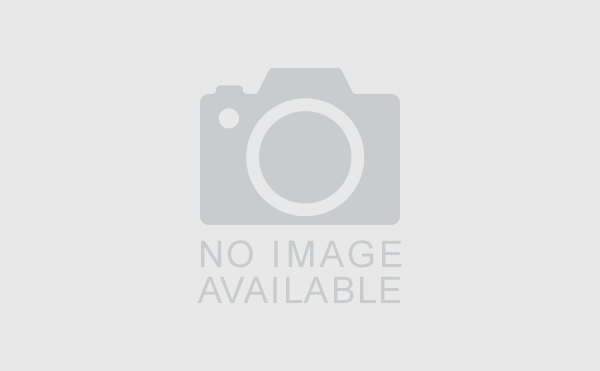「“できる支援”を、みんなでできるようにする」
ハッピースクエア火曜日ブログ担当兼管理者の牧野です。
今月のテーマは「“この仕事、向いてないかも…”と思ったときに読むやつ」。
先週は「“向いてない”と思ったら、それは成長期」というお話でした。
さて、3週目の今回は、「できる支援を、みんなでできるようにする」について。
当初の予定どおりのタイトルですが、導入は少し変えてお送りします。
“できる支援”を、文化にする
誰かひとりの“できる”に、自分が追いつけないと感じたとき、
「自分、向いてないのかも…」とつい思ってしまうことってありませんか?
でも実は、“できる人のやり方”を知って、真似して、自分なりに工夫していくことは、
プロとして大事なステップなんです。
それを繰り返すうちに、自分の中に“できる支援”の型ができてくる。
このサイクルをチームの中で回せるようになると、その職場には文化が生まれます。
「これ、あの人がやってたやつ、ちょっと真似してみた」
「こないだ〇〇さんが言ってたの、意識してやってみたらうまくいった」
そんなふうに、“できる”が共有されていくと、支援のレベルは自然と上がっていきます。
「真似る」は、学びの入り口
よく、「自分にしかできない支援」とか、「自分らしいやり方」とか言いたくなるけど、
その前にやるべきことって、たぶん“人のやり方を真似る”ことなんです。
うまくやっている人を観察して、「なんでそれがうまくいってるのか?」を考える。
それをそっくり真似してみて、やってみて、ちょっとずつアレンジしていく。
それが結局、一番早いし、深い学びになる。
最初は「自分、全然できない…」って落ち込むかもしれないけど、
その落ち込みが“成長の起点”だったりするんですよね。
「できる」を、いっしょに増やしていく
向いてるかどうか、なんて、実はどうでもよくて。
大事なのは、“できる”をみんなで増やしていけるかどうか。
誰かひとりが突出しているよりも、
「うちのチーム、支援の質がみんなで底上げされてるよね」っていう状態の方が、
ずっと働きやすいし、目の前の利用者さんにとってもプラスになる。
だからこそ、自分の“できる”を誰かに渡してみる。
そして、誰かの“できる”をちょっと借りてみる。
そうやって、みんなで育てていく支援の文化があれば、
「なんか、最近ちょっとできるようになってきたかも…」と思える日が、きっと来ます。
次回予告(8月テーマ「“この仕事、向いてないかも…”と思ったときに読むやつ」)
1週目:「それ、ほんとに“向いてない”の?」
2週目:「“向いてない”と思ったら、それは成長期」
3週目:「“できる支援”を、みんなでできるようにする」
4週目:「悩んだ経験は、必ず“誰かの支え”になる」
編集後記(夏休みっていいなぁ~)
夏休みの宿題って、
「初日に終わらせる or 最終日に泣きながら詰め込む」の二択説ありますよね。
ちなみに私は「9月になってもやってない派」でした。(2択にないですが(笑))
でも、親になった今の私は「自由派」です。
やってもいいし、やらなくてもいい。
ただし、やらないなら先生に元気よくこう言いなさい。
「やってません!!(キリッ)」
このスタンス、実は結構ガチでして。
やることの意味を自分で考えて、選んで、説明できる子になってくれたらそれでよし!
……と、思ってはいるのですが。
現実は「それでいいの!? 怒られない!?」と妻からの冷たい視線が刺さります。
妻は「やらなきゃダメ派」です。
夏休みの宿題で教育方針の違いがあぶり出されるパターン。
あっそうそう「自由研究」どこが自由なんですかね!?
テーマからして不自由だし、調べ方も自由すぎて逆に難解。
子どもに「なに調べたらいい?」って聞かれて、
「“自由研究って何なのか”を研究したら?」と返したら無視されました。
…というわけで、宿題に追われる全国の子どもたちとその家族へ。
やるもよし。やらぬもまたよし。
ただし、“やらぬなら やらぬで堂々と 言い切るべし”——それが自由派の掟です。